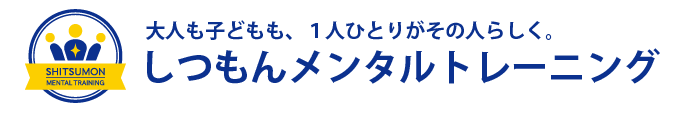大人が楽しそうに仕事をすると
子どもたちも感じ取り良い影響を受けます。
自分も楽しめているかな? と
自分自身が楽しむことの大切さを再確認しましょう。
私たちが楽しそうにトレーニングすると、
子どもたちも一緒にやりたいと思ってくれるかも。
子どもたちを楽しませる前に、まずは大人から。
目の前のことを楽しむ気持ちを大切にしましょう。

洋服が欲しくなったら必ず立ち寄る洋服屋さん。
「このジャケット、他のサイズありますか?」
と訊ねると、
「もちろんです!僕、探すの得意なんですよ!」
と、ユーモアたっぷりに答えてくれます。
僕のような素人の目では、
他のお店で販売している洋服との違いは、
はっきりいってあまりよくわかりません。
ところどころデザインは違うけれど、
あまり大きな違いが無いようにも見えるんです。
けれど、
ついついここのお店に足を運んでいるんですよね。
その理由は、店員さんがとても楽しそうだから。
そんな単純な理由で、
「またここで買おう」と思っている自分がいます。
これは、
僕ら子どもたちと関わる立場としてとても参考になります。
「自分も楽しめているかな?」
「いまの笑顔は輝いてるだろうか?」
子どもたちと関わっているいまを楽しむことを忘れてしまっては、
子どもたちを楽しませることは難しいかもしれませんし、
楽しそうなところに、
子どもたちも集まってきます。
論語には
「これを知る者は、これを好む者にしかず、
これを好む者は、これを楽しむ者にしかず」
という言葉があります。
ものごとを知ることは大切ですが、
知るよりも好きであること。
そして、好きであることよりも
楽しむことが最も重要だという教えです。
「知る」や「好む」は孤独な作業ですが、
「楽しむ」ことの延長には社会との接点があります。
楽しそうにしていると「何やってるの?」と人が集まってくるんです。
ー渋沢健(日本国際交流センター理事長)
改めていまやっていることを
「楽しむ」ことの大切さを見つめてみるのもいいかもしれません。
「いま、楽しめているかな?」
「もっと楽しむために、何ができるかな?」
僕ら大人が楽しそうに仕事をしていれば、
「仕事って楽しいんだな」って子どもたちも感じるかもしれません。
トレーニングに興味を持てず、
蝶々を探すことに夢中な子も、
僕らが楽しそうにトレーニングをしていれば、
自然と「一緒にやりたい」と思ってくれるかもしれません。
子どもたちを楽しませる前に、
まずは僕ら大人から。
目の前のことに
楽しむ気持ちを改めて大切にしましょう。
◎まとめ
- 子どもたちの学習を楽しいものにする方法を探る。
- 目標設定や努力の大切さを伝える。
- 失敗や挫折から学ぶ姿勢を育む。
- 楽しむことの重要性を再確認し、仕事やトレーニングにおいても楽しさを追求することが大切である。
- 子どもたちを楽しませるためには、まずは大人が楽しむことが重要。
- 自身の楽しさを示すことで子どもたちの参加意欲を引き出すことができる。
5,000人の読者が購読中のメールマガジン!

無料のメールマガジンに加えて、
講演会やセミナーでお伝えしている子どものやる気を引き出す5つの方法を「誰でもすぐに実践できる」ようにシンプルなかたちでお届けしています。ぜひこちらもお受け取り下さい!
オンラインスクールでさらに学びを深めませんか?
すぐに学びたい!というあなたには、
いつでも、どこでも、好きなときに学べるオンラインスクールを用意しています!
ぜひこちらで学びを深めて、子どもとの関わり方をより良いものにしましょう!