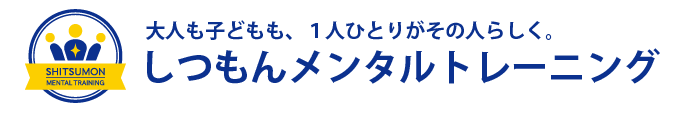練習に夢中になってほしい
集中してほしいと
僕たち大人は願わずにはいられません。
集中力は
限られた時間しか持たないことを理解し、
子どもたちの集中力状態を
観察することが重要です。
テレビゲームにおける
成功要素(自由、自己決定、遂行能力)を
スポーツに取り入れ
子どもたちに自分で選択肢を持たせ
自己決定権を与えることが役立ちます。

●どんなことで困っていますか?
低学年の子供達にサッカーを中心にスポーツを学ばせているが、
子供たちの集中力が持たない
●どんな状態を望みますか?
夢中になって遊んでくれる環境を作ってあげたい。
ご質問ありがとうございます!
今回は指導者さんからの質問です。
僕自身も
どうしたら子どもたちが
わくわくドキドキしながら夢中になって取り組んでくれるか?
を探究しています。
夢中になって取り組むことが、
学びを最大化してくれると信じているからです。
では、
どうしたら彼らの
夢中を引き出すことができるのでしょう。
集中力は続かない!?
まず、
「集中力は続くもの」という思い込みを
捨てるところからはじめましょう。
私たちの集中力は
そう長く続かないのかもしれないのです。
集中できない原因は、
- 学習環境そのもの
- 練習の内容
- 休憩や睡眠の取り方
- 体調
など様々なところに潜んでいます。
東京大学薬学部の池谷裕二教授が
株式会社ベネッセコーポレーション協力のもとに
行なった実験によれば、
学習中の中学生の脳波を計測したところ、
勉強を開始してから40分を境に
集中力が急激に降下することが示唆されたのだそうです。
中学生で40分ですから、
小学校低学年では、
さらに短いことは容易に想像できます。
集中力4つの状態
ちなみに集中力には
4つの段階があると言われています。
consciousness :ぼんやりと意識を向けているattention :注意を向けているconcentration :集中しているfocus :没頭している
子どもたちが
どの集中段階にいるのかを
興味深く観察することで、
僕たち大人の
アプローチにも変化が生まれます。
どんなときに夢中になっていますか?
子どもたちを観察していると、
「夢中になっているとき」と
そうでないときがあるはずです。
そこには
どんな違いがあるでしょうか?
どんなときは
夢中になって取り組んでいて、
どんなときは
集中力散漫になっているでしょうか。
テレビゲームに学ぶ「集中」がつづく要素
僕たちが教えるスポーツでは、
あまり集中力が続かないのに対し、
テレビゲームは
「やめなさい!」と何度言っても、
集中して取り組むのはなぜでしょう?
ここには
大きなヒントがありそうです。
大きなヒントがありそうです。
子どもたちに、
「ゲームのどんなところが好き?」
と聞いたことがあります。
すると彼らは、
- 「自由なところ!」
- 「自分で決められること」
- 「作戦考えて、戦うこと」
と教えてくれました。
つまり、
テレビゲームの中には、
自分で考え、
自分で決められる自由があり、
計画を立てて実行する(遂行能力)などの
要素が含まれているのです。
管理されてばかりではつまらない?
一方で
僕たちのスポーツ指導の現場はどうでしょう?
やるべきことが決まっていて、
言ったことと違うことをしたり、
失敗すると怒られてしまう。
また、
僕たち指導者が考えた
計画を実行し、
自分で選択する自由は
限りなく少ない。
仮にそうした環境だとしたら、
子どもたちの集中がつづかないのも
無理はないかもしれません。
学びにゲームの要素をプラスする
でも、
悲観しすぎることはありません。
子どもたちを観察し、
集中力がつづき、
夢中になれる環境づくりのコツを知ったら、
いまから実践すればいいのです。
テレビゲームの要素は
- 自由
- 自分で決められること
- 遂行能力(計画して実行する力)
の3つでした。
まずはこれらの要素を
練習に追加してみましょう。
いかがでしたでしょうか。
今回は、
子どもたちの夢中を引き出すためにできることを
簡単にお伝えしました。
できることから
少しずつ取り組んでいきましょう!
少しずつ取り組んでいきましょう!
◎まとめ
- 集中力は限られた時間しか持たないことを受け入れよう。
- 子どもたちの集中力の状態を観察し、どの段階にいるか理解しよう。
- テレビゲームの成功要素(自由、自己決定、遂行能力)をスポーツに取り入れよう。
- 子どもたちに自分で選択肢を持たせ、自己決定権を与えよう。
- 学びをゲームの要素で豊かにすることで、子どもたちが夢中になり、集中力を向上させる。
5,000人の読者が購読中のメールマガジン!

無料のメールマガジンに加えて、
講演会やセミナーでお伝えしている子どものやる気を引き出す5つの方法を「誰でもすぐに実践できる」ようにシンプルなかたちでお届けしています。ぜひこちらもお受け取り下さい!
オンラインスクールでさらに学びを深めませんか?
すぐに学びたい!というあなたには、
いつでも、どこでも、好きなときに学べるオンラインスクールを用意しています!
ぜひこちらで学びを深めて、子どもとの関わり方をより良いものにしましょう!