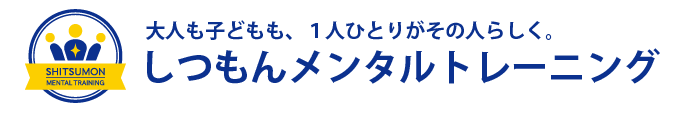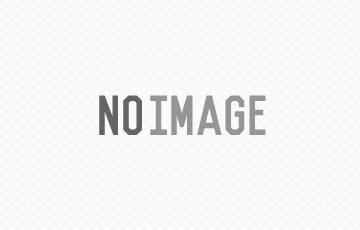いつもお読み頂き、
本当にありがとうございます!!
■ ついつい手伝っちゃう環境を作ろう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「誰だよ力抜いてるやつ!!」
子どもたち選手が
サッカーゴールを運ぶ時、
多くの場合、
こうした言葉が飛び交います(笑)
あなたも、もしかしたら
クラスみんなでやる大掃除や
綱引きの大会、
給食当番の時などに、
「ま、サボってもわかんないでしょ~」
と手を抜いたことはありませんか?
僕はあります(笑)
このような、
ついつい手を抜いてしまう心の動きを
心理学では「社会的手抜き」といいます。
チームスポーツになればなるほど、
この社会的手抜きが邪魔をしてきます。
1人だと素直でやる気がある選手も
集団になると一気に
手を抜きはじめてしまうんです。
責任の所在が分散するのが
原因かもしれません。
先日、
つくば小学校の先生のお話を
伺ったときのこと。
「先生は給食当番は
何人でやっていますか?」
という質問がありました。
多くの小学校の先生たちは
6人~10人で行っているそう。
着替えて、
食器を運んだり、
食べ物を均等によそったり、
牛乳を運んだりと
たくさんの仕事があります。
けれど、
その先生の学級の
給食当番の人数は4人。
そう、
たったの4人なんです。
「先生、
4人でできるんですか!?」
「いえ、できません(笑)」
「え、じゃあなぜ!?」
「困っている人を助ける優しさを
学んで欲しいんです。」
給食当番はそもそも4人では
ほとんど仕事にならないそうです。
けれど、
見るに見かねて、
「わたしが牛乳配ってあげるよ!」
というような子が
必ず現れるそうです。
そして、
そこを見逃さず
先生はほめることで、
その行動が波及し、
翌日にはみんなで給食当番を
するようになるそうです。
社会的手抜きは
「誰も見てないし、
気づかないからいいや~」
という心の動きから起こります。
一方で、
つくばの子どもたちは
「手伝ってあげたい!」
という気持ちから行動が
生まれています。
これがチームだったとしたら、
1年後の姿は
容易に想像がつきますよね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
手抜きをしないことこそ、
一流選手への条件
ー野村克也(プロ野球監督)
■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
人数が多くなると、
意識的ではなくても
手を抜いてしまいます。
けれど、その一方で
いくら人数が増えても
自分の仕事をしっかりと
全うしようと、
一生懸命な選手もいます。
チームで、
手を抜けない環境をつくり、
お互いを助け合う風土と
やる気を引き出しましょう。